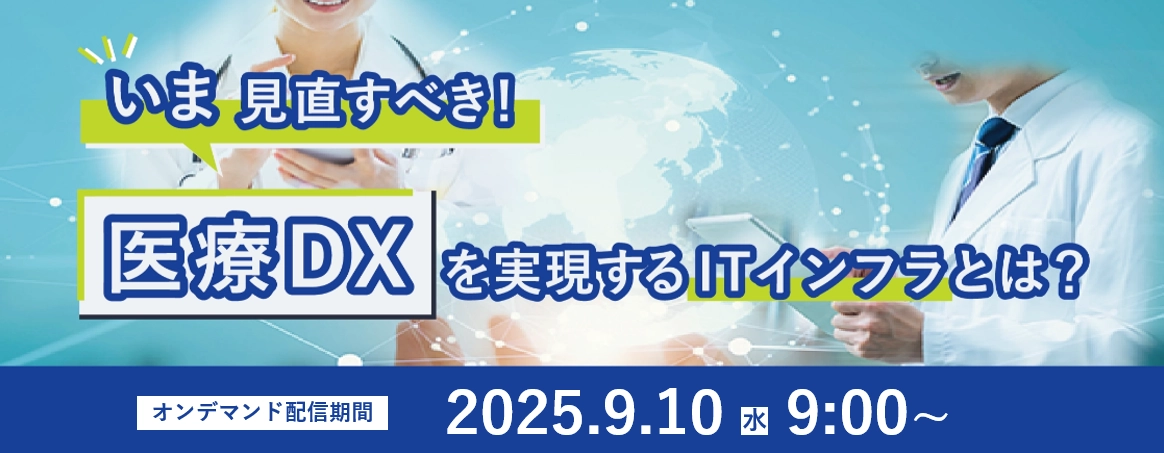サイト内の現在位置
患者さんが突然無断離院をしてしまった場合に 病院が抱えるリスクとは?

無断離院について考える
無断離院とは、入院中の患者さんが主治医の許可や外出手続きを経ずに、病院を出てしまうことです。事故や病状の悪化といった本人の問題だけではなく、家族や社会からの病院に対する信用も低下するという問題があります。
とりわけ離院中の事故では、患者本人が被害者にも加害者にもなりえるため、社会への影響が少なくありません。
無断離院は、故意に無断離院するケースと、故意ではないケースがあります。後者は認知症患者に多いため、高齢化が進んでいる日本においては近年増加傾向です。そのため、年々病院や施設でトラブルが増加し、訴訟に発展しているケースも見られます。したがって、離院対策について、適切な予防策を講じることが必要であるといえるでしょう。

(1)認知症患者など自身の状況が把握できていない場合
認知症は、自分が認識している世界と現実の世界にズレ(認知能力の低下)が生じています。その結果、入院したこと自体を認知していないため、点滴を自己抜去したり無断で離院をしたりしてしまうのです。
このため、家では徘徊といった症状が出現します。また、ズレによって不安や焦りが生じ、唐突な行動を起こしてしまうため、ムラがあるのも特徴です。
この場合はリスクが最も高いため、防止策を施す運用や施設上の工夫が必要でしょう。
(2)外出時に許可が必要なことを患者自身が認識していなかった場合
患者さん自身が入院時に説明されたことを忘れていたり、救急で入院したために、本人への説明が十分できていなかったりする場合に発生します。
患者さん自身に理解力があるため、きちんと説明をすることで理解してもらえることがほとんどです。
(3)故意に外出・外泊する場合
入院生活は、ベッド上での安静や絶食といった、非日常の生活を強いられるためにストレスがたまりがちです。
その結果、院外の空気を求めたり、家での生活に戻りたいという欲求が勝って故意に外出や外泊をしてしまったりします。私自身も過去に、喫煙をしたい患者さんが病衣のまま外のコンビニエンスストアまで出て、発見されたというケースを経験したことがあります。
きちんと説明をすることが必要ですが、理解していただけないケースもあり、退院の選択を余儀なくされることもあるでしょう。
無断離院によって生じる問題

患者目線
患者さんにとって、離院は事故や病状の悪化等を引き起こす問題があります。
平成19年12月に、アルツハイマー型認知症の方が電車にはねられて死亡するという事故があり、鉄道会社が家族を訴えたケースがありました。結果的に、家族には監督義務がなく、鉄道側の訴えは棄却されましたが、社会には大きな影響を与えました。
その他、認知症の方がデイサービスを利用中に離院し、屋外で凍死していた事例もあります。
以上のことを踏まえると、認知症の場合、離院した際の院外での事故のリスクが、そうではない人と比べて高くなると言えます。
また、病状の悪化という点においては、必要な時間に薬の投与ができなかったり、点滴針によって傷つき出血したりする可能性もあります。必要な薬剤を体内に入れることができず、病状が悪化してしまうこともあるでしょう。
なかには、離院し院外で飲酒をするアルコール性肝硬変の患者さんもおり、病状悪化を引き起こす一因となることもあります。
病院スタッフ目線
一部の隔離病棟を除くと、一般的な病棟では出入りを制限しているところは少ないでしょう。スタッフが一人の患者さんを四六時中見ていることはできないため、とりわけ出入りの激しい病棟では、部屋から患者さんがいなくなっても気づかれないことが多いのです。
そのため、看護師による検温や点滴交換、医師の回診時に初めて部屋にいないことに気づくケースもしばしば見られます。
また病院では、胃潰瘍であれば消化器病棟というように、多くの場合、病態に応じた病棟に入院します。安静度に制限がなく、食堂や売店といった病棟外の施設に行くことができる患者さんがいる傍ら、認知症の患者さんもいるという状況が発生するわけです。
さまざまな病態の患者さんが同一病棟内にいるため、スタッフ間で共有する情報が煩雑になってしまいます。
また、離院してしまっても名前だけでは捜索できないため、離院後の足取りを追うことができずに、発見が遅れてしまうことが多くなっています。
病院経営者目線
病院や施設は離院問題に対して、損害賠償を受ける民事責任、刑事罰を受ける刑事責任、行政罰、行政処分を受ける行政責任といった「法的責任」と、誠意やおわびの心といった「道義的責任」といった2つの責任を問われる可能性があります。
不法行為かどうかは、病院が安全配慮義務を果たしたかどうかが重要であり、とりわけ予見可能性や回避可能性があったかどうかが争点となります。
予見可能性があったかについては、その人が病院から出て事故にあう可能性を予測できたかがポイントになり、回避可能性があったかについては、悪い結果にならないための予防策を尽くしたかがポイントになります。
すなわち、認知症があると知っていて、かつ院外に出る可能性があると予測でき、何もしなければ転倒や事故にあう可能性が高いという患者さんの場合には、責任を問われるということです。
身体拘束をすることで制限するという方法も考えられますが、現在身体拘束については、切迫性、非代替性、一時性であるべきといわれているので、最小限の時間や程度、方法にとどめなければなりません。
認知症患者さんは自分で日常生活を送れる程度の人もたくさんおり、拘束をすることができない人が多いのです。そのため、無断離院の予防のためには、警備員やスタッフの増員など、人件費を捻出する必要も生じるでしょう。
離院問題が引き起こすリスクを未然に防ぐためには

故意に離院する場合や、許可が必要なことを知らなかった場合には、話し合いをする場を設けて納得してもらうことが大切です。その際、無断離院をたびたび繰り返すような患者さんに対しては、他の患者さんの安心した入院生活を妨害する行為であることを説明したうえで、退院していただくことまで踏み込んで話をすることも大切でしょう。
前述したように、認知症など自身の状況が把握できていない場合は、最も危険性が高いため、施設やシステムの工夫が必要です。
現場レベルでは、家族への協力依頼をしたり、スタッフが頻回に患者さんの部屋を確認したり、離床センサーをベッドの近くに置くなどが考えられます。
また、患者さんに対して決まった行動時間に、決まった行動を取れるように指導をするのも一手です。さらに、病棟内スタッフや出入り口の警備員、事務員と、離院リスクのある患者さんの写真や入院病棟などの情報を共有するのもよいでしょう。認知症患者や離院リスクのある患者さんに、蛍光テープや目印を貼って、他の人が見ても分かるようにするのも有効です。
ITを利用した離院リスクの防ぎ方
ITを利用した方法として、顔認証カメラを設置するというものがあります。顔認証カメラは、空港での出入国でも使用されるなど、安全性や質は保証されているといってもよいでしょう。病院に導入することで、外出許可が出ているかどうかを機械が識別してくれるため、人件費を抑えられ、なおかつ今働いているスタッフの労力も減ると考えられます。
IT導入にあたり注意しなければならないこと
顔認証・入退出管理システムを導入するには、個人情報登録や情報管理が重要であるため、個人情報、顔写真、顔データなどの同意の取り方に注意しなければなりません。システム管理の体制を作る必要もあります。
また、導入コストと、ITを使用しないコストの差がどれくらいあるかを知ることが必要です。さらには、他の患者さんや家族などの出入りによって扉が開いている間に、一緒に出てしまうといった問題が生じたり、開かなくて感情的になり壊される可能性があったりすることも注意しなければならないでしょう。
発行元:NECフィールディング
お客さま事業・業務にお役立ていただける情報をお届けします。
ご相談はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
※当社は法人向けサービスを提供しているため、個人のお客さまに対してはサービス提供できません。あらかじめご了承ください。
セミナー情報・お問い合わせ