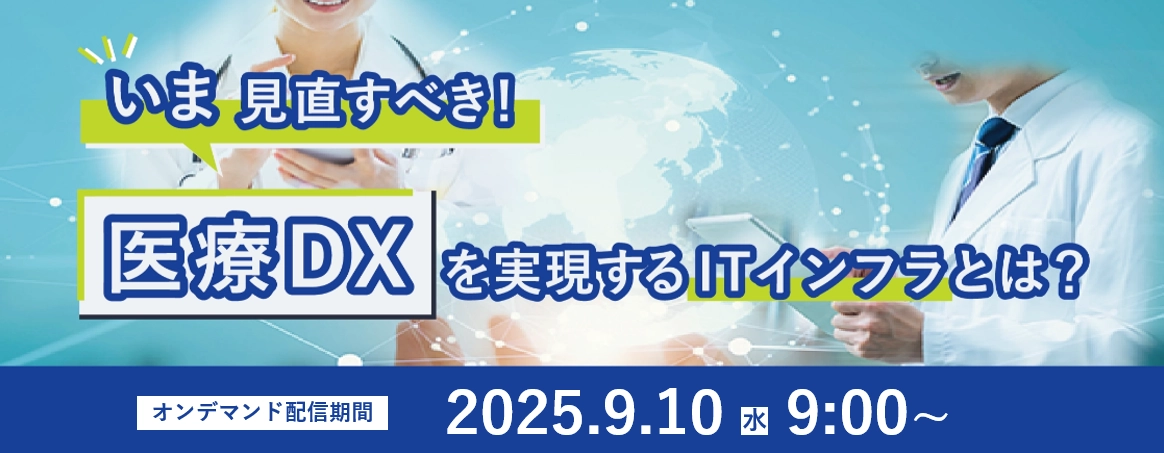サイト内の現在位置
【医療機関向け】PHSの代替となる病院内スマートフォンの活用例とメリット、通信規格について

PHSの公衆向けサービスが終了したことを受け、病院内で利用している自営PHSを今後どうするか検討している方もいるのではないでしょうか。PHSの代替手段としては、スマートフォンがあります。この記事では病院内においてPHSからスマートフォンへ移行するメリットや活用できる機能、PHSの代替となる通信規格を紹介します。
病院内PHSの代替品としてスマートフォンが注目される背景
病院内のモバイル通信の利用は、PHSからスマートフォンへと変わりつつあります。その背景には、いくつかの事情が絡みます。
医療機関内のモバイル端末利用の拡大推進
かつて携帯電話などのモバイル端末は、ペースメーカーなどの医療機器への電波の影響が懸念されていました。またマナーの観点でも節度のない利用に問題がありました。そのため不要電波問題対策協議会(現・電波環境協議会)が1997年(平成9年)に指針を定め、医療機関での「携帯電話全面使用禁止」となりました。
その後、携帯電話が一般に普及して技術が進歩し、4Gや5Gなど新しい通信規格の携帯電話では、医療機器に影響を与えないことが調査で判明しました。それまで電波の影響が懸念されていた植込み型医療機器の方も技術が向上し、携帯電話使用による影響が起こりにくくなりました。携帯電話やスマートフォンが日常に欠かせないものとなった背景も後押しして、日本の医療業界は方針を転換し、携帯電話の使用について見直されるようになりました。
近年では、日本医師会が目指す医療DXにおいて、「医療機関内のモバイル端末の利用拡大」が推進されています。
医師の働き方改革
医師の働き方改革の一助としても、スマートフォンが注目されています。医師の長時間労働については以前から問題視されており、2024年(令和6年)4月より、「医師の働き方改革」制度が始まりました。その内容は時間外労働の上限を設定し、医師個人の負担軽減を図ることで、医療の質・安全の確保、ひいては持続可能な医療体制を維持していくことをねらいとしたものです。
医師の業務の負担と時間を削減するためには、これまで以上に業務を効率化する必要があります。スマートフォンの活用は、業務効率化の方法のひとつとしても注目されているのです。
医療機関における音声通話ニーズ、PHS市場の変化
個人で契約できる「公衆PHS」は、2023年(令和5年)3月にサービスが終了しました。病院などで利用できる自営PHS(構内PHS)は継続していますが、今後PHSの市場が縮小してPHSを利用できなくなったり、PHS端末の価格が高騰したりする可能性があります。
また、スマートフォンは音声通話に加えてデータ通信も可能なことから、病院内において携帯電話に求められるニーズが変化している点も挙げられます。
病院内におけるスマートフォンの活用例
PHSの代替機器として挙げられるのがスマートフォンです。スマートフォンを用いると、PHSよりも多彩な機能が利用できるようになります。
連絡手段
PHSは音声通話のみでしたが、スマートフォンは、内線・外線電話に加えて、メールやチャット、ビデオ通話などのアプリを利用できます。グループチャットやビデオ通話により、連絡したい人物が別の病棟にいたり通話ができなかったりしたとしても情報共有が可能となります。また緊急時の連絡をスマートフォンへ一斉配信することも可能です。
ナースコール・IPカメラ連携
電話帳をシステム管理者側で一元管理することもできます。最新の電話帳情報が各々のスマートフォンに反映されるため、緊急連絡をしたい場合にも番号検索が容易となります。
端末の一台化
病院などの医療機関では、PHSは音声通話機能のみだったため、投薬などの情報管理のためにPDA端末(携帯情報端末)も併用していました。しかし、スマートフォンを活用することでPHS+PDA端末を利用していた業務を、スマートフォン一台にまとめることが可能です。
病院内でスマートフォンを活用するメリット

スマートフォンで実現可能な機能を取り入れれば、業務効率化やコミュニケーションの強化につながるというメリットがあります。
外部機器との連携が可能
スマートフォンはナースコールやIPカメラなど患者さまの状況をすぐに確認できる外部機器と連携できます。緊急の場合でも状況を迅速に把握でき、ナースコールの応答時間短縮にもつながります。
情報共有・コミュニケーション強化
連絡手段の幅が広がり連絡が取りやすくなるため、スタッフ間の情報共有をスムーズに行えます。固定電話の対応で診療や処置が止まってしまうというケースも軽減できるでしょう。
業務効率の向上
内線・外線の両方が利用可能でチャットなどの連絡手段も揃っているほか、スマートフォンアプリでさまざまな業務を行えるようになります。PHSだけではできなかった業務の質と効率の向上が期待できます。
またスマートフォンはPHSの代替のみならず、医療DXを担う機器です。導入すれば、オンライン資格確認をはじめ今後の医療DXの各施策が実施可能となります。
発行元:NECフィールディング
お客さま事業・業務にお役立ていただける情報をお届けします。
ご相談はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
※当社は法人向けサービスを提供しているため、個人のお客さまに対してはサービス提供できません。あらかじめご了承ください。
セミナー情報・お問い合わせ