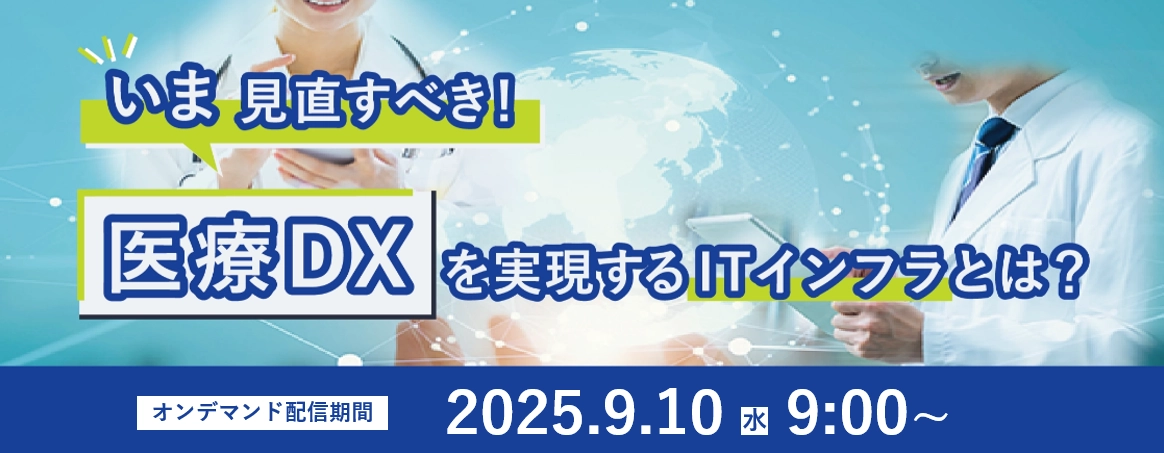サイト内の現在位置
予期しない自然災害に対して病院がするべき事前対策は?

近年自然災害が増加しており、従来は地震を中心に考えられていたが、水害を含め、その他、幅広い災害対応が、災害拠点病院だけでなく一般病院でも求められている。
災害発生時、被災地はまさに修羅場と化し、被災者は怪我で、命を落とすこともある。また、常用している服用薬などがなくなり、病気が悪化することもある。災害は待ってくれない、患者さんは待ってくれない。そのために病院としてできることはなにか。
1. 事前対策が重要視され始めた背景は
近年、東日本大震災や熊本地震といった地震による被害や大型台風による河川の氾濫、住居孤立、マンションの浸水被害がニュースとなっている。また、それらの災害による影響で仮設住宅での生活を余儀なくされたり、電気系統が浸水により故障したマンションでは、エレベーターや電気が止まるなど通常の生活が難くなってしまった方も大勢いる。
これらのことから、災害時にはライフライン機能が停止し、通常通りのことが行えない状態となることは想像に難くない。しかしながら、医療機関においては、被災したからと言って医療行為を全くのゼロにすることはできない。
そのため、災害時には災害拠点病院だけではなく、一般病院にも病院としての機能をできるだけ維持し、患者さんの受け入れができることが求められる。

2. BCP対策を考える上で災害拠点病院と一般病院の違いは?
有事の際に対して、あらかじめBCP(Business Continuity Plan 事業継続計画)の策定を行うことが必要である。BCPとは、企業が自然災害、大火災など緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことである。
ここで、災害拠点病院とは、平成8年に当時の厚生労働省の発令によって「災害時における初期救急医療 体制の充実強化を図るための医療機関」が策定され、その後平成24年に改正があり、災害時における医療体制の充実強化について、現在は下記の9つの運営体制を満たした病院である。
- ① 24時間体制の緊急対応
- ② 被災地からの傷病者の受入れ拠点
- ③ ヘリコプターによる傷病者、医療物資等のピストン輸送を行える機能を有する
- ④ 災害派遣医療チーム(DMAT)の保有及びその派遣や受け入れ体制を有する
- ⑤ 救命救急センター又は第二次救急医療機関
- ⑥ 業務継続計画(BCP)の整備
- ⑦ BCPに基づいた研修及び訓練の実施
- ⑧ 地域医療機関との定期的な訓練の実施や支援体制
- ⑨ ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できること(努力義務)
災害拠点病院においては近隣の医療機関と連携し役割分担を踏まえておくことや、大量の災害時トリアージを想定した人員確保、DMATの派遣なども視野に入れておくことが一般病院との違いである。なお、基幹災害拠点センターは、各都道府県に1か所以上、地域災害医療センターは二次医療圏ごとに原則1か所以上整備されている。
一方、一般病院はそのような中心的な機能を持たないが、医療機能を維持して患者さんに医療を提供するという部分は同じである。
災害が起こると、発災直後、超急性期、急性期、亜急性気、慢性期、中長期といった6つの医療救護活動フェーズに分けることができる。災害直後は外傷が多く、慢性期から中長期のフェーズでは慢性期医療が必要となる。
一般病院において、これらを考慮した医療提供が必要である。
災害直後には入り口でトリアージを行うと同時に、院内では治療を行うといった、救急外来としての役割を果たすことが求められる。慢性期においては、医療資材の確保や慢性期治療が必要な患者に対しての対応が求められる。
では、医療機関において機能を維持するとはどういうことなのか。それはヒト、モノ、情報を安定させることであるといえる。
つまり、職員の安否確認や招集を行い医療ができる体制を整え(ヒト)、医療行為を維持するために設備を整え、備蓄を保管し(モノ)、患者さんの情報を失うことなく、すぐに取り出し把握すること(情報)が一般病院にも求められる課題といえる。
3. 災害時にICTを活用することによるメリット
災害が発生した際に、ICTを活用して継続すべき業務や
医療機関の職員/病棟・機器・消耗部材/インフラ設備を支えられるか
BCPを策定するにあたり、ヒト、モノ、情報の維持が医療機関としての機能維持をするということは前述したとおりである。迅速に職員の安否確認を行うことで人の確保を行い、電子カルテで患者情報を把握することで安心した医療提供を行うことができる。また、非常設備を整え、非常食や非常飲料水、薬剤などの確保も必要である。
災害発生時に病院を受診してきた目の前にいる患者さんに対して、より多くの患者を診るためにも、ICTを活用し職員の業務を少しでも軽減することが望ましい。
総務省の報告でも、次なる大災害に向けたICTインフラとしてクラウド等の活用を可能とする標準の備えが重要であると言われている。これは自治体などに求められている課題であるが、病院などの事業所においても最優先に解決すべきことであろう。
これらのヒトモノ情報のいずれにおいてもICTを活用し業務を継続できることが求められるといえる。
なお、BCP策定後はBCM(Business Continuity Management)として、BCPを継続的に維持管理し改善を図っていく必要がある。防災対策は事後対応の対策に目が行きがちである。しかしBCP策定においては、事前予防の視点が必要。事前予防がベスト、事後予防はセカンドベスト。日頃から、防災の事前予防を重要視する組織文化作りも大切である。
4. 災害発生時に業務を円滑に解決するためには?
そのためには、職員間の安否確認サービスを活用し、医療提供できるヒトの確保や自家発電、耐震免振システムなど、電子カルテの患者情報の確保を行うために、停電に強いシステム構築、ネットワークの多重化や情報のクラウド化などの対策が必要。
同時にメールやSNS等による情報発信手段のメディア活用のノウハウやリテラシーを日頃から職員等に教育してくことも必要である。
また、備蓄非常食、非常用飲料水、薬剤やその他医薬品の管理も通常業務の中でローリングストックをしながら使用していたとしても、使用期限の管理や発注作業は手間のかかるもの。これらを管理できるシステムがあれば災害時のみならず通常業務の効率化が図れる。
日頃から災害時におけるICTの活用を意識していくことで、我々が最も最優先すべき、命を救う活動に集中できる体制を整えていける。
発行元:NECフィールディング
お客さま事業・業務にお役立ていただける情報をお届けします。
ご相談はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
※当社は法人向けサービスを提供しているため、個人のお客さまに対してはサービス提供できません。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ