サイト内の現在位置
BCP(事業継続計画)とBCMの違いとは?策定の流れや運用方法を解説
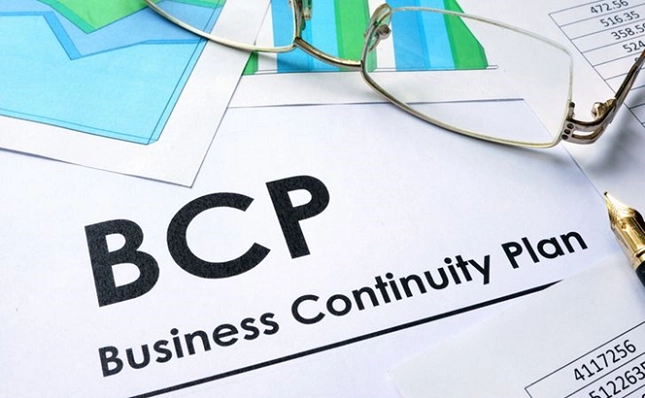
近年日本では、災害の頻発とともにコロナ禍にも直面し、企業としての対応を考える機会が増えています。そこでこの記事では、企業の社会的責任とも言われるBCP(事業継続計画)について、概要や策定の流れ、運用のポイントなどを紹介します。
BCP(事業継続計画)とは?
BCPとは「Business Continuity Plan」という英文の頭文字を取った略称で、和訳すると「事業継続計画」となります。事業所が災害やテロ、大規模システム障害などにより事業停止の危機に直面した際も、業務継続や早期復旧を図るための適切な方策を記載した計画書を指します。
BCPとBCMの違い
BCMとは、企業や組織があらゆる災害や危機に備え、事業継続を確保するための実践的な手法やプロセスのことで、Business Continuity Management(ビジネス・コンティニュイティ・マネジメント)の略称です。
BCMには、事業継続計画の策定や実行、リスク分析やリスクマネジメント、訓練や模擬演習、復旧・復興などさまざまな要素が含まれます。企業や組織がBCMをしっかりと実施することで、災害や危機発生時の被害を最小限に抑え、事業を継続していくことができます。
BCPは、具体的な非常時の事態発生時における取り組み計画書のことで、Business Continuity Plan(ビジネス・コンティニュイティ・プラン)の略称です。
つまり、BCPは企業や組織が災害時に事業継続を確保し復旧するための計画書であり、BCMはその計画を策定し、実践し維持するための一連の総合的なアプローチです。また、BCPは単発的な取り組みであり、一度策定されたものは現実に起こった時に実行されるものです。一方でBCMは日常的に取り組み、事業継続を確保するために常に対策を練り実践を継続することが必要です。
BCP(事業継続計画)の目的
BCPの目的は先述のとおり、企業が危機的状況に瀕した際に適した行動をとることで事業の停止を回避し、万が一停止に追い込まれた場合も早期復旧を図ることです。
経営戦略としての側面も
BCPは緊急時に役立つだけでなく、企業としてどの業務を優先して取り組むべきかなど、業務の優先度の洗い出しも可能となり、経営戦略の見直しという側面でも有用です。
企業やブランドの価値向上にも
BCPの整備は、企業自体の信頼性やイメージの向上につながり、顧客や取引先に選ばれやすい企業づくりの一環にもなります。
BCP策定の流れ
自社でBCPを策定し運用するまでの流れは、以下のようになります。
1.方針の策定と人員体制の確立
BCP策定によって自社が何をめざすかを明確にし、想定される緊急事態やリスクを検討して方針を決定します。その上で適した人員を選定し、計画書の作成と実際の対策にあたる社内体制を決めていきましょう。
2.BCP発動時の優先事業や行動体制を決定する
緊急時にどの社内事業を優先するかを決め、実際に事業継続や復旧活動にあたるチームなどの体制を決めます。
3.計画を文書化し、社内に共有・周知する
策定した計画を全従業員が確認可能な文書にまとめ、全員が確認できるよう共有を行います。中小企業庁が計画書のフォーマットを提供しているため、それらを活用しても良いでしょう。
BCPを策定する際の注意点とは?
BCPを自社で策定する際には、以下の注意点を踏まえて計画を立てましょう。
1.自社に適した計画とする
他社の優秀なBCPに則って自社でも策定したいと考えるかもしれませんが、それが自社に適しているとは限りません。完璧を求めるよりは、自社の経営環境や対応可能なレベルに即した実現・実行可能なBCPの策定を心がけましょう。
2.計画書の検証や見直しを定期的に行う
時代や企業規模などが変化すれば、それまで最適だったBCPも内容の見直しが必要となります。定期的に計画やマニュアルの内容を検証し、自社のBCPに基づく行動実績があればそれらも踏まえて見直し(改訂)を行いましょう。
【BCPの運用】災害発生から復旧までの対応方法
緊急事態の発生から復旧までの、BCPに基づく対応方法は以下のとおりです。
1.初動対応
災害であれば人命を守る行動や安否の確認、システム障害であればネットワークの即時遮断など、被害を最小限に抑えるための初期行動にあたります。
2.仮復旧
初動対応の後は、使用できない設備の代替対応やバックアップデータを活用してのデータ復旧、被害状況に応じた取引先変更などの対応にあたります。
3.本復旧
仮復旧が済んだら、平常業務に戻していくための取り組みに着手します。事業所の建物やライフラインの復旧確認、業務状況のチェックなどを実施しましょう。
4.保守運用
1~3までの行動計画をいつでも適正に運用可能とするための、平時の活動です。緊急連絡先の変更にともなう更新、避難通路の検証・見直し、防災備蓄品の入替、定期的な避難訓練の実施などです。
BCPを上手く運用するポイント
BCPをスムーズに運用するには、まず簡易な形で良いので早期に策定し、運用しながら実効性向上を図るべく更新や改訂を行っていくと良いでしょう。
中小企業庁では、以下の運用方法を提案しています。
定着
全従業員にBCPを周知し理解を促すため、研修などの教育活動を実施します。
見直し
経営状況や環境の変化に応じ、内容を見直します。下記の「RTO」「RLO」の2指標を基にすると良いでしょう。
RTO(Recovery Time Objective):復旧までの目標時間・日数
RLO(Recovery Level Objective):平時の事業水準の何パーセントまで復旧可能か
BCP運用にあたり「体制構築」が重要
BCPを策定することは災害発生時に迅速かつ正確な対応をするための基盤づくりの一環でもあります。しかし、BCPを策定しただけでは災害発生後に対応することは難しいです。策定したBCPにあった運用ができるよう、運用体制を整えることが重要です。
その例として、BCP運用チームの編成が重要です。BCPを運用するための専門チームを編成し、チームメンバーの役割や責任を明確にします。また、チームメンバーの代替要員を決定し、体制の代替可能性を確保しましょう。
次に、トレーニングの実施も重要です。BCPを実行するためには、BCPに適した知識や技術を持った人材が必要であり、BCPを運用するために必要な技術や知識を身につけるよう、定期的なトレーニングを実施することが大切です。
最後に、BCP運用体制の定期的な継続性確認も忘れずに行いましょう。BCPを策定した後、BCP運用体制の定期的な継続性確認を行うことで、BCPを運用する体制が維持されます。万が一の際に運用体制が機能しないといったことが起こらないよう、BCP対策が有効に機能しているかを定期的に確認すべきです。
このように体制を整えることで、事業継続性(BCP)の確保、リスクマネジメントの強化、スピーディーな復旧・復興に繋がり、企業のイメージの損失を低減することが期待できます。
まとめ
2011年の東日本大震災やコロナ禍を機に、企業のBCP対策が大きく注目されています。未策定の場合や、策定から1度も見直しをしていない場合は、昨今の情勢に合わせたBCPの計画立案や改定を検討してみてはいかがでしょうか。
NECフィールディングでは、リモートワーク導入支援やデータセンターから非常食・避難生活用品まで、BCPを支援するさまざまなサービスや製品を取り揃えております。BCPの策定や運用についてお悩みをお持ちの企業さまは、ぜひ一度お問い合わせください。
発行元:NECフィールディング
お客さま事業・業務にお役立ていただける情報をお届けします。
※当社は法人向けサービスを提供しているため、個人のお客さまに対してはサービス提供できません。あらかじめご了承ください。
 中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」
中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」